

加賀健二さんが語る
フランコ・ミヌッチさんと
〝洋服屋〟の心意気
談/加賀健二
写真・構成/山下英介
2022年3月、筆者がとてもお世話になったイタリアファッション界の大物、フランコ・ミヌッチさんが86歳で逝去された。フィレンツェという街を象徴するような洋品店「タイ ユア タイ」を創設し、その洒落た装いで日本でも話題を集めた彼の訃報は、ひとつの時代の終焉を感じさせるものだった。ファッションがどんどん〝記号〟へと移り変わっていく今という時代にあって、ひたすらに美しい装いを追い求めた彼の生き方とその功績を、改めて多くの人に知ってもらいたい! そんな思いで、かつてフランコさんのパートナーとして活躍し、現在はフィレンツェで「タイ ユア タイ フローレンス」を経営するとともに、ネックウエアブランド「アット ヴァンヌッチ」を手がける、加賀健二さんにインタビューを依頼した。〝洋服屋〟という言葉に秘められた、粋なおじさんたちのプライドを感じとってほしい。
DCブランドから
クラシックファッションの道へ

今日は、この3月に惜しくも亡くなられたフランコ・ミヌッチさんのことを話したくて、その人となりを最も知る日本人、加賀健二さんのもとにお邪魔しました。
加賀 ぼくがフランコさんとお仕事をしたのは16年くらいでしたが、本当に面白い方でしたね。今日はなんでも聞いてください。
ぼくは「タイ ユア タイ」以前の加賀さんを知らないのですが、この業界におけるキャリアはどこから始まったんですか?
加賀 もともとは大学卒業後、大阪の生地メーカーに入ったんですよ。実は工学部出身で、エンジニアの内定ももらっていたんですが、ファッション好きな友達に付き合って面接だけ受けに行ったら、ぼくだけ受かってしまって(笑)。
理系だったとは初めて聞きました! ではそれほどファッションに興味はなかったんですか?
加賀 いや、もともと父親がアメリカ好きで、古着を買ってもらったり、サーフィンをやっていたり、中学生の頃から西海岸ファッションに親しんでいました。
それがどうやって、イタリアンファッションに開眼したんですか?
加賀 DCブームは一応かじったんですが、17〜18歳くらいのときに、〝イタリアもんはええらしい〟って噂で聞いて。映画の『アメリカン・ジゴロ』を観てジョルジオ・アルマーニの存在を知ってからは、もう取り憑かれたようにイタリアンデザイナーに傾倒していくんです。ぼくたちの周りでは、完全にブームでしたね。アルマーニやヴェルサーチは10代で経験していました。
1964年生まれの加賀さんが、10代でアルマーニを着るというのは、かなり早熟ですね! 大阪というエリアの特異性もあったんですか?
加賀 実は当時、インポートウエアのマーチャンダイジングは大阪で組んでいたんです。先に大阪に輸入して、それを東京に持っていくというビジネス。いわゆる輸入商社も大阪の企業ばかりでしたし、1970年代後半から80年代後半にかけて、大阪にはすでにインポートものが集まっていました。東京より1年は早かったですね。

アルマーニから、いわゆる〝クラシコイタリア〟という流れはどうやって生まれたんですか?
加賀 その生地メーカーを3年で辞めて、独立したんですよ。それでイタリアに行って、工場をまわって在庫の洋服を買い付けたりして、得意先に売る。当時はファクトリーもののニットなんて珍しかったから、なんでも売れましたよ。毎月ボーナスの時代です(笑)。
イタリアが買い物天国と呼ばれていた時代ですね。
加賀 そのときに印象に残っているのは、イタリアのファクトリーの裕福なオーナーたちって、みんなフルオーダーを着ているんです。で、土日はラルフローレン。ぼくがアルマーニを着ているというと、「知らんな」って。もちろんわざとですよ。
リアル富裕層の世界を垣間見たわけですね。
加賀 30歳くらいのときはパリでウィメンズの仕事をしていたんですが、そのときまわりにいたユダヤ系のお金持ちも、みんなオーダーのスーツ。時計はジャガー・ルクルトで、ウエストンやジョンロブの靴を履いてるわけ。しかもみんなぼくより歳下なの。ホテル・プラザ・アテネのレストランで会食したときなんて、ぼくだけペラペラのDCスーツで、すごく肩身が狭かったのを覚えている。全然スタートラインにつけてないじゃんって。そこで初めてジェイエムウエストンに行って、シューズをオーダーするんです。
フロムファーストビルから始まった
本場のクラシコイタリア

それが加賀さんとクラシックとの出会いなんですね!
加賀 そう。それで日本に帰ってきたら、友人が「タイ ユア タイ」を開店する話を持ってきたわけです。
おお、運命の出会いが! そこで初めてフランコ・ミヌッチさんを知るんですか?
加賀 いや、以前から「タイ ユア タイ」はいかした店やなって、思ってましたよ。当時世間的には全くの無名でしたが、「信濃屋」の白井俊夫さんや「成毛商会」の成毛賢次さんといった大御所の皆さんはご存じだったと思います。直訳すると「ネクタイちゃんと締めようね」っていう店名なんですが、あれは現地のスラングで、「さっさとしなさい」みたいな意味があるんです。店内はとてもいい匂いだし、なんて粋で洒落たお店なんだろうって。
確かに「タイ ユア タイ」といえば、サンタマリア・ノヴェッラの香りが印象に残っています。
加賀 そんなお店とたまたまお仕事ができるようになって、1996年8月に最初にお店を構えたのが、表参道にあるフロムファーストビルの2階。あそこは業界的には〝出世ビル〟として有名だったんですが、フランコさんはもともと路面にできると思っていたから、最初から平謝りですよ(笑)。
96年というと、雑誌が〝クラシコイタリア〟を扱い始めたくらいですかね。
加賀 そうですね。でもお金持ちの間では、クラシックファッションはぜんぜん知られていませんでした。ロングホーズを売っているお店すらなかったし。だから逆風からのスタートでした。

美意識の固まりだった
フランコ・ミヌッチさん

当時のフランコさんはどんな方でしたか?
加賀 彼の経歴は面白くて、もともと20世紀FOXで、映画の配給をやっていたんですよ。その後はロンバルディア州でベネトンの営業をやって、それからレップ(営業代理人)。そこで成功して、「タイ ユア タイ」を構えたらしいですよ。
のちにファッショニスタとして知られる娘婿のシモーネ・リーギさんは、当時からいたんですか?
加賀 いましたね。彼はいつもダブルのスーツを着て、葉巻をくわえて、それをお店の入り口の石壁の隙間に置いてるの(笑)。あのキャラの濃いふたりが、お店の前にふたりで腕組んで立ってたら、入りにくいですよね。
確かに威圧感ありますね(笑)。しかしあのお店は、フィレンツェでは売れていたんですかね?
加賀 1984年にオープンしたのですが、最初の7年は赤字だったようです。お客さんはフィレンツェ市内というより、プラトーとか郊外のお金持ちが中心。それと外国人ですね。営業上手な人だったんで、ぼくもずいぶん買わされましたよ。出張に行くと、いつも「スーツ何着持ってきたんだ?」と聞かれて、答えると「それじゃダメだ」なんて言われて(笑)、まんまと買わされてしまう。
ああ、昔のクラシックファッション業界の方々は、出張時に異常なほど洋服を持ってきていましたよね(笑)。
加賀 彼が来日したときにトランクを見せてもらったんですが、一回の出張に軽い引っ越しくらいの洋服を持ってきていました。で、アイロンがないと怒るの。あと宿泊するホテルも、プラスチックのコップが置いてある部屋には泊まりませんでした。「俺は囚人じゃねえんだ」と。これは名言ですね(笑)。
ものすごく美意識の高い方でしたよね。
加賀 そう。一回京都の料理旅館にフランコさんを泊めたとき、風呂の入れ方がわからないって呼び出されて駆けつけたら、座布団を5枚敷いて、椅子のようにして座っていました(笑)。で、お風呂に入った後も、浴槽や床をピカピカに拭いて、あたかも入っていなかったようにしてから出てくるんです。たった今風呂に入ってきた、みたいに思われるのは恥ずかしいんでしょうね。
確かに一度ご自宅に伺ったときも、チリひとつないピカピカのお家で驚かされました。

加賀 ホテルの朝食だって、待ち合わせた時間に行くと、絶対にその前にご飯を済ませて、ばっちり着替えて、優雅にコーヒーを飲んでいるわけ。うちのスタッフがビュッフェで山盛りにしているのを見ると、ものすごい怒っていましたよ(笑)。●●●じゃねえんだからって。
美意識のない行為だと(笑)。ぼくがよく覚えているのは、出張で日本に来ていたとき、毎日ホテルからお店へ向かう道すがらに花を一輪買って、真っ白なコットンコートのフラワーホールに挿してから出勤していたことです。
加賀 そうそう、グレンフェルのコートにね。あれは彼の役者なところで、イタリアではやらないんです(笑)。日本の皆さんにええ格好をしたいわけですよ。ぼくたちに対しても「今日はパンツのクリースが甘いな」とか、「靴のコバが剥げてるな」とか、とてもうるさいの。そんな人だから、歩道の段差でちょっとコバを擦っただけでももう大変。「俺、もう今日は無理や」って落ち込んじゃって、職人に鉄コテを当ててもらってました(笑)。

ちょっと塗り直すとかでは回復できないんですね。とことん業の深い方ですね(笑)。
加賀 結局ぼくたちは勉強が嫌いで洋服屋になっているわけでしょう? それだったら洋服屋らしく生きなくちゃだめだ、ということはよく言われましたよ。
〝洋服屋〟としての心意気というかプライドは、フランコさんのみならず、往年のクラシックファッション業界の皆さんからは強烈に感じましたね。
加賀 生活のリズムやルーティンも完全に決まっていて、手を洗う石鹸も、新聞も、カフェもレストランも決まっていて、絶対にそれを崩さない。どんなに忙しくても、スターバックスのサンドイッチは食べませんでした(笑)。洋服だって、同じようなものしか買いません。タンスを開けると、170番手双糸の白シャツをズラッと何十枚も並べていて、そのすべてにアイロンをかけた後、第一ボタンが開かないようにマチ針を打ってたから(笑)。
マ、マチ針まで! そういえばジーンズにもアイロンをかけて、ばっちりセンタークリースを入れていましたもんね。
加賀 そう。ブティックみたいなクローゼットでした。極めてオーソドックスな嗜好で、スーツは冬だとサキソニー系生地で、柄はヘリンボーンかストライプ。夏はリネンかシルクウールリネンの三者混、それか14ミクロンのウール。仕事でもプライベートでも、安い生地は絶対に着なかったですね。フルオーダースーツも大量に持っていましたが、結局袖を通すのは半分以下。ちょっとでも違うな、と思ったらもうダメなんですよ。
〝不完全〟という美学の象徴
「セッテピエゲ」というネクタイ

当時の「タイ ユア タイ」ではキートンやアットリーニの既製スーツを扱っていましたが、普通のものとは全く違いましたよね。
加賀 全部モディファイしてね。肩パッドを抜いてアームホールを細くして、ドロップ8にして・・・といった具合で、キートンなら18箇所いじってました。ほかのお店では絶対にやらない仕様です。ちなみにロータで現在も扱っている「フィレンツェ」というモデルは、フランコさんが別注した仕様だったのですが、エクスクルーシブにはしなかったので今でも買えますよ。
そういう神経質なほどに完璧主義な方だったのに、つくっていたネクタイは芯地を使わず7つ折りにした「セッテピエゲ」というのが、不思議といえば不思議ですね。マリネッラあたりと違って結び目がきっちりと決まるネクタイではないし、しかも妙に長いという。小剣を長くしてずらす、〝小剣ずらし〟という小ワザ、流行ったなあ(笑)。
加賀 あの人は、完璧主義は格好悪いという考え方なんですよ。いかに決めていないように見せるかっていうところに、命を懸けるタイプだったんです。そしてスタイルとはある意味では不便なもので、全員から拍手を浴びられる商売ではない。売れているものを売るんだったら、俺は必要ないだろう、と言っていました。ネクタイに関しては当時152㎝という決まりがあったので、合わない人はダブルノットで締めてください、という世界ですよね(笑)。
あのネクタイはフランコさんの発明だったんですか?
加賀 もともとアメリカに似たようなものがあったらしいですよ。それをヒントにして、自分なりに型紙を引いて、つくってくれる工場を探したんです。あれは厄介なシロモノで、ヘムの巻き縫いは慣れればなんとかなりますが、畳んでまつって留めていく工程は、生地の地の目に沿って職人が自分の感覚でずらしていかなくてはならないので、とても難しいんです。手間がかかるわりには儲からないので、産業としては成立させにくいんですよね。
※セッテピエゲ製法についてはこちらを参照。
まさに工芸品ですよね。日本市場においては、すぐ理解されたんですか?
加賀 東京でお店を開けてから5年くらいは、本当に売れなかったですね。こういうある意味での不完全さを売りにするようなネクタイは、日本のファッション文化に存在しなかったですから。だからあえてお店の前面に出して、徹底的に宣伝をしたんです。10年くらい経って、卸を始めてからですよ。これでやっていけるねって言えるようになったのは。

なるほど。ある意味では不完全を極めたのがフランコ・ミヌッチさんのスタイルなんですね。
加賀 ちょっとダスティン・ホフマン似で(笑)、別に男前でも、身長が高いわけでもない、しかももうおじいさんに近い年齢の方がああいうスタイルをしているという点が、新鮮だったんでしょうね。スーツにマリーニのタッセルローファーを合わせて、セッテピエゲのネクタイを締めて、股上の深いロータのベルトレスパンツをはいて、ペルソールの眼鏡をかけて、オーデマ・ピゲの『ロイヤルオーク』。それとサンタマリア・ノヴェッラのフランジパーネの香水ね。どれも当時はマニアックなブランドでした。このあたりが流行ったのは、明らかに彼の影響だよね。
当時大ブームだった雑誌『LEON』で大々的に取り上げられたこともあって、どれも2000年代半ばに、とても流行りましたね。
加賀 ひとつの文化をつくりましたよね。スーツにスクエアトウのタッセルローファーなんて、ルール的には完全にアウトだもん。でも、実はパパスが大好きで、来日したときはいつもお店に行ってたんですよ(笑)。「ここはいいね」って。
それは意外ですね(笑)。どこか通じるところがあったのかなあ。
加賀 趣味である山登り用のアウターなんかを買っていくんですが、みんな不思議に思っていました(笑)。
「わがまま」と「勝手」の
違いって何だろう?

しかし、そういう強烈な美意識を持った人と長年仕事を続けてきた、加賀さんも相当すごいですね。
加賀 クラシックファッションは「タイ ユア タイ」が初めてだったし、まあ、すごく鍛えられましたよ。フランコさんとチーロ・パオーネさん(2021年に逝去されたキートンの前総帥)が見ている前でバイイングするわけだから。向こうもお前のところは安い生地いらないよな、みたいな感じになっていて、サイズと数を記入してから、最後に値段を書かれるわけ。ジャケット一着のFOB(商品の卸値と船に積むまでの経費を含めた価格)2000ユーロ・・・うーん、仕方ない、みたいな(笑)。
うわあ。最初に値段を教えてくれないんですね。
加賀 買うって決めたんだから、いくらだろうと関係ないでしょ?という世界です。最初に価格を聞くなんて、行儀悪いことしないでね、という美意識。ぼくがここで怯んで定番のシャークスキンありませんか?なんて言ったら、フランコさんは怒って帰ってしまいますよ(笑)。
昔の紳士服業界はハードコアだなあ(笑)。残ったらどうしよう、とか考えないんですか?
加賀 お店に並んだときに美しいか、美しくないか、ということを一番大切にしていましたね。その〝絵〟がきれいだったら、ぼくたちも楽しいし、お客さんも喜んでくれる。守りに入ったときは、たいていダメなんですよね。売れ残ったからって、モノが悪かったなんて考えない。たまたまお知らせの仕方が悪かったか、やることが早すぎたな、と思わないと。だから悲観的になったことはありません。ただ、ここまで上質なモノで勝負するお店は、もう存在しないでしょうね。だって馬鹿げているもん(笑)。
今にして思えば、2007年に青山の根津美術館近くにつくった「タイ ユア タイ」の旗艦店は、もう空前絶後でしたよね。あれほど流行に関係ない高級既製服をストックしたお店なんて、もはや世界中どこを探してもない。「アルニス」に匹敵する存在だったと思います。
加賀 現在は「アーツ&サイエンス」になっている場所ですが、フランコさんもあのお店にはとても喜んでいました。2階に富裕層の顧客がくつろげる20坪の応接間をつくって、靴職人の早藤良太さん(現在はミュンヘンで活動)や、今や日本NO.1と名高い「サルトリア チッチオ」の上木規至(のりゆき)さんといった腕利き職人を囲うとともに、3階に修理工房をつくり、全部自社で洋服を直せるようにしました。運転手付きの車に乗ったお客さんがいらっしゃるのは、だいたい平日の2時〜5時。普段会えないような方々ばかりで、本当に社会勉強になりました。
あのお店は、極めてヨーロッパ的な感覚でしたよね。「イルミーチョ」の深谷秀隆さんも、「タイ ユア タイ」から世に出た才能のひとりです。今ではすっかり定着している日本のオーダー職人の世界を、いち早く捉えたのがあのお店だったと思います。
加賀 ぼくたちは2000年代初頭からこういう時代がくることはわかっていたので、キートンやアットリーニのお客さんに我慢してもらってでも、日本の職人を応援していました。フランコさんも、若い才能に対してはとても寛容でしたし。そういう意味では、ぼくたちもちょっとはこの業界に対して役立てたのかな、とは思いますけれど。本当に濃い日々を過ごさせてもらいました。
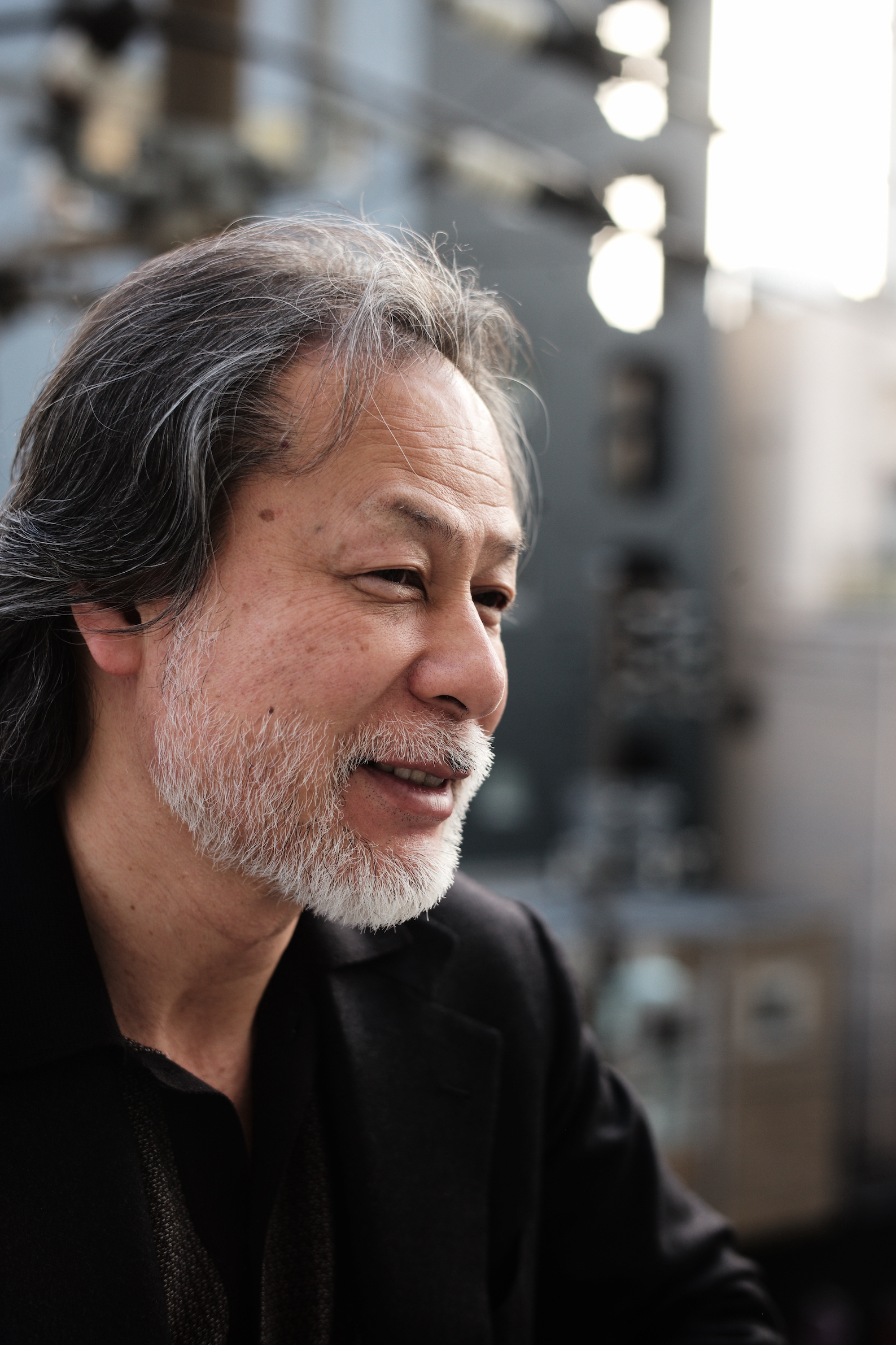
加賀さんがフランコ・ミヌッチさんから学んだことって、なんですか?
加賀 う〜ん、たくさんありすぎて一言では言い表せませんが・・・。モノは好きだけどモノに振り回されないこと。モノよりも生き方にこだわること、かなあ。彼のまわりには大金持ちになった仲間がたくさんいて、彼だっていくらでもそうなれるチャンスはあったけれど、まわりに流されることなく、フィレンツェの小さなお店で、自分らしく生きることを選んだ。彼は接客と、セールスという仕事が大好きだったんだよ。そして、彼がそんな生き方を貫けたのは、奥様や周囲の支えがあったからだと思います。みんな彼のことが大好きだったから。
どんなに若いバイヤーや顧客にも、決して手を抜かず一生懸命もてなして、セールスしている姿が思い浮かびますね。そこにはある種のやせ我慢の美学を感じさせましたが。
加賀 彼が事務所に出勤するときは、みんなのためにトリュフ入りのパニーノやドーナツを買って、コーヒーも淹れてくれる。それだけで毎日100ユーロずつ消えちゃうんです。ぼくもそういうフランコさんに影響を受けているから、やせ我慢してないとは言われへんなあ(笑)。
ぼくたちが運営していた「タイ ユア タイ」に集まっていた方々って、みんなわがままは言うけれど勝手なことはしないんです。たしなみがあって、阿吽の呼吸で繋がることができた。まさにフランコ・ミヌッチさんはそんな人で、本当にわがままばかりでしたが、絶対に勝手なことは言いませんでした。もうあんな人、二度と出てこないだろうな。
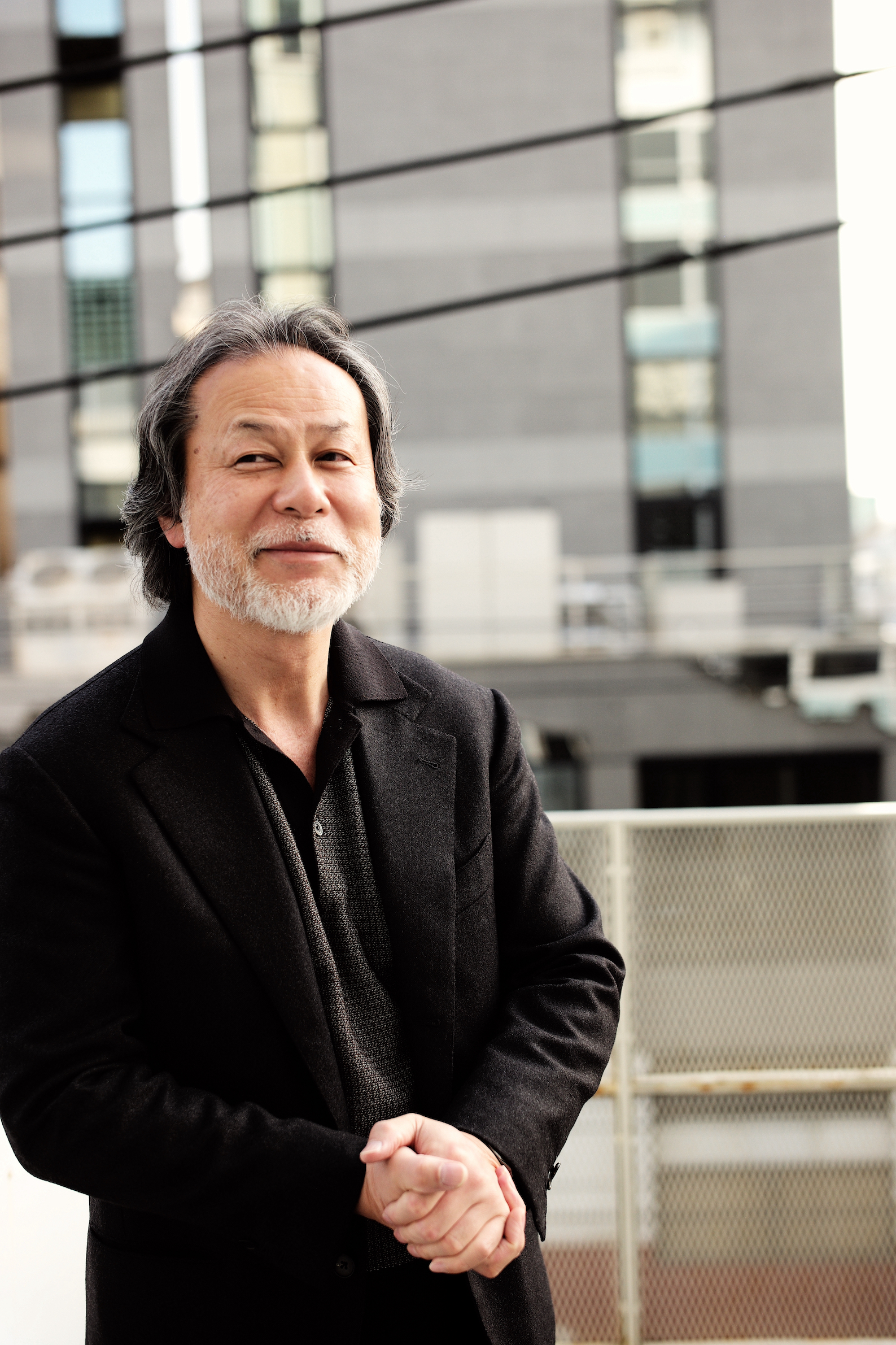
1964年生まれ。1996年に「タイ ユア タイ」の日本上陸に参画、日本におけるクラシコイタリアブームの立役者のひとりとして活躍。2011年からはフィレンツェで「セブンフォールド」社を興し、現地にネクタイ工房を構える。現在はフィレンツェの旗艦店「タイ ユア タイ フローレンス」を拠点に、アット ヴァンヌッチをはじめとする伝統工芸のようなネックウエアブランドを展開。日本とイタリアを行き来しながら、その魅力を世界に伝える。